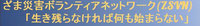後期第3回講座(12/4)の様子
後期第3回講座は、下記を実施しました、講座には秦野市から小清水危機管理官にもご出席
いただきました。
①9:00-10:30 講義 『被災地支援活動事例から 避難所生活を考える 』
講師: 自衛隊神奈川地方協力本部 平塚地域事務所所長 三上俊和氏
自衛隊の業務紹介に続き、3.11東日本大震災での災害救援活動において果たした
役割と、現地での生々しい救援活動をお話し頂いた。現場では自己の感情を抑制しな
がらの活動を行ってきたが、振り返ると当時の悲しい場面を思い出し辛くなるとのこと。
直接、お話しを聴くことで改めて自衛隊の皆様に深い感謝の気持ちを新たにしました。
②11:00-12:00 講義 『災害に備える』
講師: 消防庁殿
総務省消防庁は全国を統轄する立場。発災時の警報、避難、家庭でできることなど、
具体的な防災知識と行動についてお話しいただいた。
地域消防団組織が減少傾向にあり、学生含む若年層との連携が課題。参加者からは
地域に密着している婦人会、シニア層との連携もこれから必要ではないかとの意見も。
本講話に際しては、神山洋介衆議院議員のご紹介をいただいたもので、講話に先立ち
ご挨拶を頂いた。(前期第2回講座ではご講話いただいています。)
③13:35-16:00 模擬体験 災害救援ボランティアセンター設置訓練
訓練スタッフ 当会メンバーによる
ボラセン立ち上げ訓練は3回目になるので、今回は、今までの復習を兼ねてのもので
した。訓練を通じて、どうすればボラセン昨日が効率よく、効果的にできるかを考える
良い機会となった。最大の課題は、やはり、ボランティア受付け業務を如何に効率よく
行うかであった。𩙿ん楝は当会メンバーを含め、16名が参加。



後期第2回講座(11/23)の様子
後期第2回講座は、下記を実施しました。
①9:15-12:00 イメージTEN(静岡県の自主防災会向け防災訓練ゲーム)
ゲームの解説と事例による訓練ゲームを4班に分かれて実施しました。発災後に
起こる家屋倒壊、道路不通、火災、けが人の救助など、時間の経過と共に、
「何をすべきか」「何ができるか」について検討と発表を行いました。
各班の対応の違いを知ることもゲームの効果でした。
②12:00-13:00 宇宙食を食べてみよう
前期講座に続いて2回目なので、2種類の味の違いを比較したり楽しい昼食風景
でした。
③13:00-15:00 講演「私達を取り巻く災害環境」 橋本茂氏(日本防災士会常任幹事)
「防災情報新聞」編集長として、災害の現場を見て回り、教訓や課題などを
多くの方に紹介されてきた体験のエッセンスをわかりやすくお話し下さった。
・教訓は出尽くしている。しかし、それを如何に伝えるは、の難しさ
・熊本県益城町の事例 生死は紙一重 一瞬の機転と判断が命を救った
・地震直後なら車中泊はが命を救うことあり。
・行政は「公平・平等・前例」という見えない呪縛に陥りやすい
・防災担当はマイナーな立場であることが目立つ
等々。
また、聴講者からも多くの質問が出され、丁寧に回答をいただいた。
④15:15-16:00 発災時に役立つツール
・小嶋浩義氏による怪我人を搬送する道具として、不燃布を使った担架や、
身近にできるジーパン再利用の布担架の作り方を紹介いただいた。
・大江正行氏によるロープワークの実習
ほんむすび、もやいむすび、など。皆さん、コツを習得したようです。
後期第1回講座(10/15)の様子
後期第1回講座は、下記を実施しました。
①9:15-12:00 秦野市消防による「救護・救命」研修
前期講習では基礎研修でしたが、今回は、救護・救命の知識と実習でした、
実習では、幼児に対してのAED操作、心肺蘇生についても行いました。
②13:15-16:00 災害救援ボランティアセンター立ち上げ訓練
3.11での体験による、ボランティアセンター・スタッフ経験で学んだこと、
センターでの役割の復習のあと、実技として、机を運ぶところからのセンター設営と
ボランティア受付・マッチング・資材貸出、送り出し・帰還までの一連の流れを行い
ました。
講座では、Q&Aを通して、受講者からの活発な意見交換がなされました。
当日は、参加希望者の多くが他の行事との重なりなどで、参加者は5名でした。